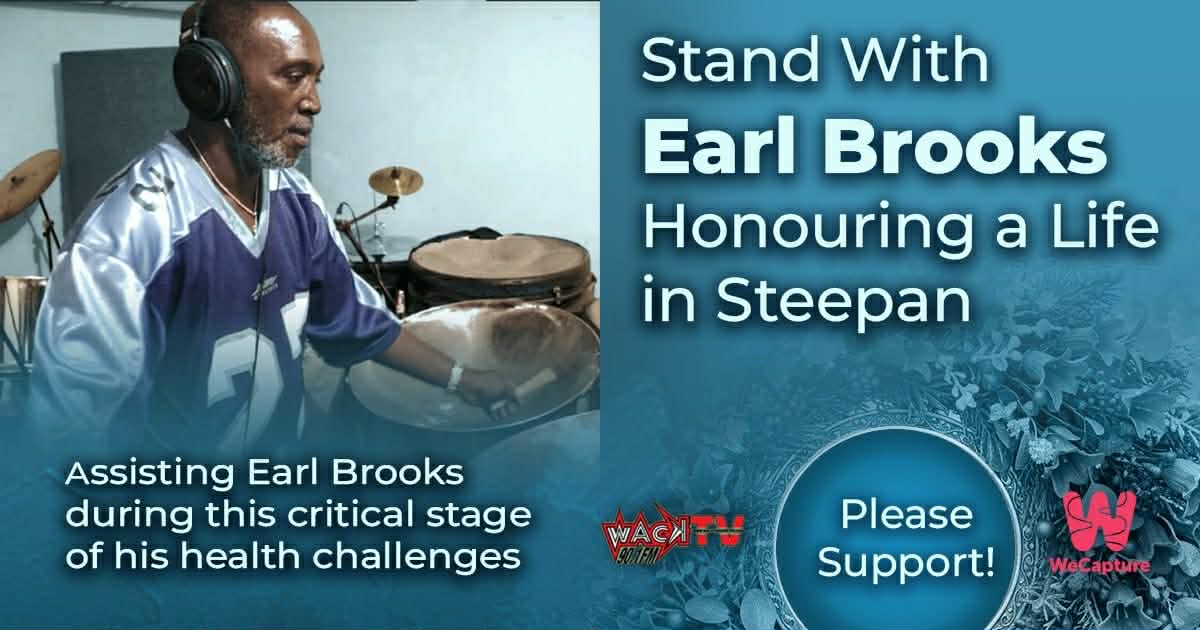トリニダード・トバゴといえば、今や世界中で演奏され、親しまれているスティールパン。もはや有名な話ですが、ドラム缶からできています。やはり、産油国であり、身近にドラム缶があった事が発展の理由でしょうか。
しかし、その生い立ちには壮絶なドラマがありました。
もともとはアフリカ系奴隷の間で竹を打ち鳴らす楽器、「タンブー・バンブー」が演奏されていましたが、竹は壊れやすいなどの問題があったため、だんだん、金属のバケツや缶、瓶をスプーンでたたく「ボトル&スプーン」などに移行していきました。
そのうちに55ガロンのドラム缶にくぼみをつけると音階が出来る事が発見され、今のスティールパンの原型になっていきます。最初は奴隷の集合禁止令などで迫害されることも多かったようですが、次第に認められ、1951年にはイギリスの博覧会で演奏するまでになります。そこからも進歩は続き、1963年、初のパノラマコンペティションが開催され、現在に至ります。
スティールパンの種類は主に、おなじみのメロディーを演奏する単体楽器、テナーパン、少し低い音域で伴奏をしたり、副旋律をとったりする2個で一つのダブルセカンド、中間で伴奏をするギターパン、チェロパン、そして最大ドラム缶12本で一セットという巨大なベースパンなど、ほかにも沢山の種類ががあります。
そして、スティールバンドにもいろいろなカテゴリーがあり、スモールバンドでも30人~50人、ラージバンドだと120人ものプレイヤーが演奏します。まさに壮大な音のパノラマといって過言ではありません。
そして、トリニダード・トバゴにとどまらず、世界でも活躍しているスティールパン奏者は沢山います。有名なところでは伝説のベーシスト、ジャコパストリアスのバンドに参加していたオテロ・モリノウや、オノ・ヨーコなどとも共演しているロバート・グリニッジ、日本では数々の名曲を生み出し続ける巨匠原田芳宏氏などがあげられます。
現在は日本にもたくさんのバンドや、コミュニティーがあるので、段々より身近な楽器になってきています。
<<参考文献>>
Nalis: Steelband
MITTCO:History of The Steelpan
スティールパンについてより詳しくなれる映画: スティールパンの惑星
(文・ Japanist Sayori)